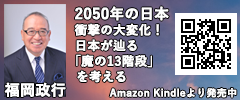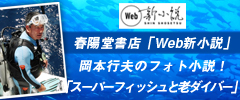- TOP
- コラム
- 上田克己のダジャリスト時評
- 第37回『2024世界選挙イヤー~試される民主主義【後編】』

第37回『2024世界選挙イヤー~試される民主主義【後編】』
『2024世界選挙イヤー~試される民主主義【後編】』
「史上最大の選挙イヤー」の2024年がスタートして3ヶ月近くになる。すでにロシアを含め20ヵ国に迫る国・地域で行政のトップや国会議員の選挙が行われた。それらを点検すると、「民主主義の前進・成熟」が伺えるケースは残念ながら乏しい。
やはり世界の「民主主義は後退している」のか。「民主主義の危機」のカギを握るのは6月の「EU(欧州連合)議会」と11月の「米国大統領」の選挙だろう。特に米大統領選は「2024世界選挙イヤー」のクライマックス。その結果が世界の「民主主義の行方」を左右する。2つの選挙を展望し、なぜ現代世界にとって「民主主義が重要」かを考えたい。
米国と並んで世界の「民主主義の先進国で、先導役」を努めて来たのがEUと英国、ノルウェーなどの欧州諸国。
その欧州の27ヵ国が加盟するEUの「5年に1度の議会選挙」が6月6日から9日にかけて行われる。EU各国ではこの数年、「極右政党」の台頭が目立つ。この流れがEU議会選へも波及、欧州の「民主主義の行方」が懸念されている。
背景には中近東、アフリカから押し寄せる「難民・移民」問題がある。これにウクライナ戦争による「欧州内難民の発生」が加わった。
更に「ウクライナ戦争」によってロシアからの天然ガス・石油の供給がストップ。エネルギー・食糧の供給不足や物価高が国民生活を圧迫、政府への不満が強まっている。EUの気候変動対策の環境規制などで肥料、燃料も高騰、これに抗議する農民の「トラクター・デモ」もEU各国に広がっている。
こうした状況で、「難民・移民の排斥」を主張、ポピュリズム政策を掲げる右派政党が支持を集め、イタリアやオランダの国政選挙でも第1党に躍り出た。「民主政治の優等生」とされて来た北欧のスウェーデンやフィンランドでも右派政党が勢力を拡大。この流れで6月の選挙ではEU議会も「右傾化」が一段と進むのではないか、との観測が有力。
しかし、EU各国は政治課題の外交対応には意外と「柔軟でしたたか」。ギリシャが発端の「ユーロ危機」や「英国のEU離脱(Brexit)」などEUは「危機」に幾度も直面したが、「たゆたえども沈まず」(パリ市庁舎の紋章に記された標語)存続して来た。
最近のEUは「離脱・分裂」の気運は鎮静、加盟希望の周辺国がむしろ増える状況。EUを離脱した英国は経済力が低下、7つの海を支配した昔日の面影は無く、「大航海」ならぬ「大後悔時代」を迎えている。年内にも実施される総選挙では保守党から労働党ヘの「政権交替」の可能性が高い。そうなれば、「EU復帰」の世論が高まりそう。
こうした流れの中でEUの結束に唯一、抵抗し、「独裁政」を強めて来たのがハンガリー首相のオルバン。「EUの名折れ」「腐ったリンゴ」とまで揶揄され、「ハンガリーのトランプ」とも言われた。そのオルバンもEU首脳会議でドイツ首相のショルツに「コーヒーでもいかが」と促され、退室した間に「ウクライナのEU加盟交渉開始」が「全会一致」で可決された。更にオルバンはフランス大統領のマクロンやイタリア首相のメローニに説得され、ウクライナヘの「(財政・軍事)追加支援」を承認した。
オルバンを説得したイタリア初の女性首相のメローニは、15歳でネオ・ファシスト党に参加、ムッソリーニを礼賛、「民主主義を脅かす欧州で最も危険な女」と独誌に評された。それが首相に就任すると「反EU・親ロシア」からEUは「私達の共通の家」、対ロ戦の「ウクライナを全面支援」へ変身した。G7メンバーでは唯一、参加していた中国の「一帯一路」構想からの離脱も表明した。メローニは今年はG7の議長を務める。
彼女と並んで女性初の欧州委員長のフォンデアライエンは「続投(任期5年)を表明」、「最も重要なのは民主主義」と主張、プーチンと対決する姿勢を鮮明にしている。医者で7児の母のスーパーレディ。ドイツのメルケル政権の女性初の国防相。メルケルが欧州政界を去り、「もしトラ(トランプ大統領の復活)」となれば、EU首脳で「トラ狩り(トランプに対抗、説得)」が出来る「リーダーは不在」となっていた。
フォンデアライエンとメローニの2人の「金髪美女」の登場は、「鉄のお嬢さん(orお母さん)」と呼ばれたメルケルに替わって「美女と野獣」の対決を演じられそう。EUの美女連合は「米国のトラ」だけでなく、戦狼外交の「中国のオオカミ」、「ロシアのシロクマ」に対しても「民主主義を守る戦いに挑む」覚悟が窺える。
NATO(北大西洋条約機構)にフィンランドとスウェーデンが加盟、メンバーは32ヵ国と増え、EUとの連携も強めている。
欧州はパッチワークのように小さな国が寄り合っている。それらの多様な国々が、なぜ「民主的な交渉・話し合いで、まとまれるのか」。それは、この100年余りだけでも2度の大戦と、戦後も冷戦を経験し、「平和・共存・自由」の貴さを痛感したからだ。各国首脳・政府間の「コミュニケーションの密度」が濃く、一般国民レベルの交流も活発。国民の「民主主義・自由主義を尊重する意識」は程度の差はあるが浸透している。
だからEU議会が若干右傾化しても、EU各国に「右傾化のドミノ現象」が起きる心配は無さそうだ。
「民主主義の危機」が心配なのは、むしろ米国だろう。第1次大戦以降、「世界の民主主義の伝道師」を自認して来た米国にとって今年の大統領選はこれまでに無い「異常・異例な選挙」になる。その「異常さ」が「民主主義の後退」を招く要因となりかねない。
米大統領選は予備選のヤマ場の「スーパーチューズデー」を終え、4年前と同じ「民主党バイデンと共和党トランプの再対決」が確実となった。
その「異常さ」は、①米国史上嘗てない「高齢者対決」。
バイデンは現在、米大統領の最高齢記録を日々更新しており、11月の投票日には82歳、トランプは78歳となる。米国民の平均年齢は約38歳とG7で最も若い。この年齢ギャップから有権者にはどちらの候補も嫌いな「ダブル・ヘイター」が増えている。これでは投票率は上がらず「民主主義は進化しない」。
②米国史上初の大統領経験者の「刑事被告人」が大統領選挙の候補者。
共和党候補のトランプは4つの刑事訴追を受け、90件超の罪状が挙げられている。更に民事だが、詐欺事件などで巨額(約4億5千万㌦超)の賠償金支払いも命じられている。
その刑事訴追の内容は「不倫の口止め料支払い記録の改ざん」から大統領選の敗北を認めず、「選挙結果の操作」を政府や州議会関係者などへ要求、最終的には「国会議事堂襲撃を扇動」へとエスカレートした。トランプは「大統領特権の免責」などを盾に全て「無罪」を主張しているが、果たして司法がどんな判断をするか。民主主義の根幹でもある「米国の司法の独立」も問われている。
トランプは大統領在任中もメディアから批判されると「フェイク」と片付け、耳を貸さない。そして自らがSNSを使い大量の「フェイクを発信」し続ける。
ワシントン・ポスト紙の「ファクトチェック」では在任4年間の「嘘の発信・発言」は3万573回を記録した。
トランプはメディアや議会から不正を追求されると「魔女狩り」と反発して来た。「魔女狩り」とは「社会的弱者・異端者が言われない制裁・迫害を受ける」例え。米国大統領という「世界最高の権力者」には当たらない。「無知な誤用」と言える。
トランプの「罪と罰」はまだ確定ではないが、その「量の多さ」と「民主主義の根幹を蔑ろにする言動」、「知性と品性に欠ける行為」に驚くばかり。
加えて大統領としての適格性が疑われるのは、「反科学性」。新型コロナによる米国の死者数は2023年9月初めの時点で117万人超に達した。この数は世界の国で断トツに多く、2位のインドの2倍以上。米国史上、最大の戦死者を出した南北戦争の死者数の倍近い。
なぜ米国は「コロナに敗北」したのか。原因は政府の感染対策の初動の遅れ、ウイルスの感染力の軽視などにある。それは「チャイニーズウイルス」と叫び、中国非難を続け、WHO(世界保健機関)からの脱退など政治的言動に走り、具体的な足元の感染対策を怠ったトランプの責任が大きい。トランプは「CO2の排出が気候変動の原因」との説に懐疑的で、地球温暖化防止の「パリ協定からの離脱」も表明した。
それでも、目下の世論調査では、接戦州でも「トランプが優勢」の結果が出ており「もしトラ」どころか「ほぼトラ(トランプの当選濃厚)」が有力になっている。「米国の民主主義」、引いては「世界の民主主義」にとって由々しき、「ヤバイ」事態。
だからこそ、敢えて「やバイ(やはりバイデン)」に期待するしかなさそうだ。僕は米国の「民主主義が機能すれば、バイデンが勝つ」と見る。4年前も「トランプ優勢の予測が多かった」が、トランプは1期で終わった。それは米国に「与野党均衡の政界、体制批判力あるメディア、中央政府から自立した自治体、強い組織力の労働組合」が存在し、「民主主義が機能した」からではないだろうか。
現代世界において「民主主義がなぜ大事なのか」。いつも引かれる言葉は英国の首相チャーチルの「民主主義は最悪の政治形態と言われて来た。他に試みられたあらゆる形態を除けば」の演説。チャーチルが「民主主義は最悪」と言ったのは、苦い経験があったからだ。彼はヒットラーのドイツを降伏させ第2次大戦を勝利に導いたのに、その直後の総選挙で、労働党に敗れた恨みがあった。それでも国民の「選挙による意思表示で政権が交代する」民主主義に「納得」し、「独裁のブレーキになる」と理解したのではないだろうか。
今年はチャーチルの演説から77年、没後59年になる。英国はこれまで保革の「強い対立」がありながら、「適時な政権交替」が行われ、チャーチルが愚痴った「最悪の民主主義」が生き延びている。英国の例を見るまでも無く、民主主義が機能するには、出発点の「選挙」が、「自由に、公正に、公明に」行われなければならない。
ところが、「2024選挙イヤー」の「世界の選挙」を眺めていると、ロシアに見られるように「立候補の自由が無く、選択肢が限定され、投票が強制され管理された」選挙では、いかに投票率や得票率が高くても「民主主義選挙」とは言えない。それどころか、選挙が「独裁」を産み育てる「選挙独裁国家」の出現が散見される。
今年は「生成AI(人工知能)元年」と言われる。これまでのSNSに続いてAIが選挙に使われ始めている。それが選挙の効率化や広報活動に役立つならいい。「偽情報の発信や対立候補の誹謗中傷」などに利用されれば、「民主主義は後退する」。現代の国家や社会の運営には「民主主義は欠かせない」。だから我々は「民主主義を守り、育てて行かなければならない」。
しかし、選挙で生まれた「独裁政治」は「選挙が根幹」の「デモクラシー(民主主義)」ではリセットは難しい。体制変革は「エモクラシー(感情主義)」とも言うべき「人間の怒り、憤慨」といった「感情のうねり」が引き起こす(英国の歴史学者ニーアル・ファーガソン)。習近平やプーチンが細やかなデモや抗議活動でも神経質に取り締るのは「エモクラシーを恐れている」からだろう。
ロシア大統領選の1ヶ月前に極寒のシベリアで獄死した反体制派指導者、アレクセイ・ナワリヌイが点けた「エモクラシーの灯火」は消えていない。妻、ユリア・ナワルナヤが夫の「諦めない」との遺志を継いで「活動の継承」を宣言した。プーチン政権下では、政敵や反体制派の人物の暗殺や不自然死が相次いでいる。ユリア・ナワルナヤも夫と同様、「命懸けの活動」となる。この「美貌の反体制活動家」を西側メディアは追い続けるだろう。それが「エモクラシーの灯火」を大きくして行くのではないかと注目したい。
モスクワで大規模はテロが発生したが、「暴力」による体制変革は大きな犠牲を伴う。「エモクラシー」が大衆を動かした先に「デモクラシー」の出番がある。そうした体制変革が望ましい。(敬称略)
2024・3・23
上田克己
プロフィール
上田 克己(うえだ・かつみ)
1944年 福岡県豊前市出身
1968年 慶応義塾大学卒業 同年 日本経済新聞社入社
1983年 ロンドン特派員
1991年 東京本社編集局産業部長
1998年 出版局長
2001年 テレビ東京常務取締役
2004年 BSテレビ東京代表取締役社長
2007年 テレビ大阪代表取締役社長
2010年 同 代表取締役会長
現在、東通産業社外取締役、日本記者クラブ会員
趣味は美術鑑賞